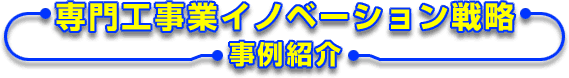

21世紀を迎え,今後ますます少子・高齢社会が進展してゆく中で,建設産業における若年入職者の確保・育成が大きな課題となっている。 「専門工事業イノベーション戦略」(平成12年7月建設省策定)において専門工事業のイノベーション事例100選が紹介されているが,その中から今回は,(株)大崎建工(東京都江戸川区)を紹介する。 (株)大崎建工は,大崎建設(株)の現業部門を担う会社として発足し,建築工事の主に躯体部分を専門とする工事業者であり,企業内訓練校や富士教育訓練センターを活用した「多能工」育成および「グループ多能工」として活用を図り,生産性の向上を図っている企業である。
「躯体一式」の専門工事会社である大崎建工は,企業内訓練校や富士教育訓練センターを活用し,社員の躯体多能工の育成を行い,多能工をグループ化して活用することにより施工の生産性向上(工期短縮)を実現している。 大崎建工がこのグループ多能工を推進するにあたって工夫したポイントとしては, 1) 訓練校の教育方法の整備 2) ゼネコンの元請経験者を職長として採用し,グループ多能工のサポート体制を構築 があげられる。 最終的には訓練生の一人ひとりを多能工にすることが目標であるが,限られた訓練期間で複数の技能力を高めることは難しいことから,多能工によって編成されている各施工班を有機的に連携して工事を進めている。 具体的には,新入社員は,基礎的な多能工の教育終了後,とび班,鉄筋班,型枠班のいずれかの班に配属され,各班でリーダー(訓練校卒業生)が,それぞれ鉄筋,型枠,とび,コンクリート工事を新入社員にOJT教育を通して,単能工としての施工能力の向上を図っている。 大崎建工の現場では,一人が複数の職種をカバーするのではなく,基本は単能工として施工に当たるが,多能工の教育を終えていることで,周辺職種も理解していることから,他の班をカバーすることが可能であり,実際,とび班の受け持ちが早く終わった場合には,型枠班の応援をするなど,それぞれの班を有機的に連携させ,3つの班をグループとして施工に当たらせている。 つまり,とび班,鉄筋班,型枠班の一人ひとりが多能工であり,それぞれの班が多能工班である。 大崎建工がこのグループ多能工を推進するにあたって工夫したポイントとしては,「訓練校の教育方法の整備」があげられる。 大崎建工に入社した社員は,まず4月から8月中旬まで,富士教育訓練センターの「建築基礎多能工Aコース」を受講することとなる。 富士教育訓練センターでは,多能工の基礎訓練のほか,新人職員訓練も行っていることから,社会人としてのマナーを身につけることが出来るとともに,鉄骨の建て方など実際の施工が体験できることから,初期の教育訓練として富士教育訓練センターを活用している。 8月下旬から9月下旬までは,訓練校において,富士教育訓練センターで不足していた座学を中心とした教育を行い,訓練終了後,とび,鉄筋,型枠のそれぞれ1ヶ月間のOJT教育を行い,1月より再び訓練校で座学を行うこととしている。 初期の知識をもとに実際の施工を行い,再度訓練校で確認をし,より確実なものにしていくというプログラムを実践している。 多能工の最大のメリットは,少人数での現場施工が可能である点があげられるが,工事の規模や場所に左右されることが多い。 大崎建工におけるグループ多能工の活用事例でも,生産性が上がる現場と上がらない現場があるが,多能工は単能工より現場にいる時間が長いことから,現場を総括的にみる視点を各自が持てば,様々な施工上の工夫が生まれるメリットがある。実際,38階のマンションの施工例では,ある一定の階以上の施工効率が著しく上昇しているケースが検証されている。 また,ただし,下請け工事だけでは,効率の良い現場が確保できるとは限らないことから,直用技能者を抱えることを武器に,直接の受注も視野に入れている。 実際の施工に関しては,多能工を指示する職長やリーダーの存在がポイントとなっており,大崎建工では,現場での経験や施工計画の経験の浅い各班を指導する人材として,ゼネコンの現場経験者を職長として組み込み,多能工グループの指導及び元請業者との打合せ調整を行っている。 大崎建工では人材育成のポイントとして,「育てる人材像の明確化」をあげている。 それぞれ職種や規模に応じた「人材の育成」があるべきであり,大崎建工では「多能工」の活用を企業戦略として取り組んでおり,そのために「多能工」を育成しているが,多くの企業が企業戦略の前に,人材育成のための訓練校を作っているのではないかと考えている。 今後,大崎建工では,単能工以上に現場全体の流れを把握し安全管理,工程管理,品質管理等に中心的役割を果たす多能工の育成を目指し,育成システム・教育カリキュラムのより一層の充実を図り,今以上の成長を目指している。 現在,工事量の減少に伴い,各企業内訓練校が非常に厳しい環境におかれていることから,建設産業の人材育成について,建設産業界として考える時期にあるのではと大崎建工の内藤社長は語っていたのが印象的であった。
|
|||||||||||||||||||