  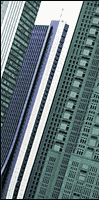 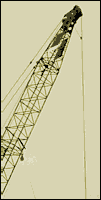  |
 |
 野田證二(のだ・しょうじ) 1936年,東京都台東区浅草生まれ。55年に東京都立蔵前工業高等学校建築学科卒業後,大友組入社。66年より大友建設(株)代表取締役。現在,東京建設業協会評議員および第四支部副支部長。建設業労働災害防止協会台東分会分会長。 |
| 西野 |
|||
| まずは大友建設さんについてお話を伺いたいのですが,ずいぶん古くからあられる会社なんですね。 |
|||
| |
|||
| 野田 |
|||
| 歴史だけは一人前なんですよ(笑)。創業は大正12年7月で,ちょうど関東大震災が起こる約2か月前ですね。私の父,先代の野田友之助が創業したわけですが,実はその前に祖父である野田浅次郎も大工職人でした。私の会社がある東京・浅草では,江戸時代から大工は自分の名前に“大”の字を付けた屋号を名乗っていて,私の祖父は「大浅」(だいあさ)という屋号でした。 私の父は,さらに近代的な建築家を目指しまして,名称を「大友組」(だいともぐみ)と改め,創業しました。 その後,私が社長となった昭和41年に大友建設(株)とさらに社名を改め,総合建設業へと業務内容も変わりました。 ですから,祖父の代から数えると,私で三代目になります。 |
|||
| |
|||
| 西野 |
|||
| 業務内容はどういったことをされているのですか。 |
|||
| |
|||
| 野田 |
|||
| 先代が官公庁の仕事も手がけるようになって,現在は民間が70%,官公庁が30%ぐらいの割合になってます。ただ,私どもはこの浅草という下町の地域の中で育ってきた会社ですから,基本はやはり住宅ですね。あとは,事務所や店舗,住居とマンションが一緒になっているような建物などが主な業務です。 大体,建設業というのは,扱っているものが,大きいものだと超高層ビルなどになり,やはり会社として手に負えるものとそうでないものがありますから,今は自分たちの得意な分野で展開するようにしています。 私が先代から会社を受け継いでもう36〜37年になりますが,よく言われている企業30年寿命説からすると,良しとしなければいけないのでしょう。企業の成長が止まってしまうケースをよく聞きますけれども,後継者がいなければ,最近のような厳しい世の中では,会社の存続すら大変な時代です。当然,当社にとっても厳しい時代なのですが,その厳しさをクリアする若い力が当社にはあると思っています。 私には娘が3人いて,娘婿が私の後継者として4代目を目指してガンバッテいます。 |
|||
| |
|||
| 西野 |
|||
| 大友建設さんの経営方針についてお聞かせください。 |
|||
| |
|||
| 野田 |
|||
| 今はやりの言葉ではありませんが,「お客様第一主義」を会社の基本精神としています。これを推進するために,私をはじめとして全社員が,誠心誠意をモットーに創意工夫・改善に努め,安定した安全と技術と高品質をもってお客様の信頼を獲得することに取り組んでいます。私たちの仕事はものづくりですから,いくら一生懸命にやってもその姿勢がお客様に通じなければだめです。やはり,お客様にいかに満足していただき,100%に近い納得をしていただくかが一番大事なことです。 |
|||
| |
|||
| 西野 |
|||
| 大友建設さんのセールスポイント,誇れる点は,どういうところですか。 |
|||
| |
|||
| 野田 |
|||
| そうですね,やはりこの地域で100年という実績があるわけですから,そういう点でも,当社のつくった建物,作品については,他社に負けないものづくりをしていると思っています。 先ほど,企業の寿命30年の話をしましたが,やはり,リズムのいいときと悪いときがあります。当社も世代交替の時期を迎えている中で,最近の作品は,例えばこの浅草でいいますと,地域に長年ある神社の建物を受注したり,テレビで放映されるような建物の作品に携わったりしています。これは,先ほど述べた当社の「お客様第一主義」の姿勢が,そういった仕事の受注につながっていると思っています。また,いま「第二の創業への挑戦」をスローガンに活動しているところです。 |
|||
| |
|||
| 西野 |
|||
| これからは,大きな作品といいますか,大きな建物にもどんどん参加していらっしゃるのですか。 |
|||
| |
|||
| 野田 |
|||
| 大きいということは必ずしもいいことではなくて,私たちがいわゆるスーパーゼネコンのようなところに立ち向かっても,それは当然,勝ち目はないわけです。今まで私たちが経験してきた建物というと,中高層のものになるわけで,それ以上の建物をつくろうという夢は,持たないようにしています。 身分不相応な営業展開はやはり難しく,私が今まで見てきたところでは,会社規模を小から中,中から大へ展開したときに,その多くが挫折しているんです。ですから,会社の規模を大きくするにしても,まず社内の人材教育がしっかり行き届いていないとだめですね。挫折した会社は,そういう人材教育の上でうまくいかなかったところがあったように思います。そういうことを長年,見てきたのですから,その経験を生かして会社を経営しています。 |
|||
| 西野 |
|||
| 建設業界ではIT化が進められていますが,大友建設さんではどのような取り組みをなさっていますか。 |
|||
| |
|||
| 野田 |
|||
| 同レベルの会社と比べると,当社はかなり進んでいると思います。情報伝達がすぐにできるように,社内はもちろん,現場もLANでつないでいます。当然,1人1台,パソコンを持っています。これが,当社の大きなエネルギーの1つになっていると自負していますね。 | |||
| |
|||
| 西野 |
|||
| 早い時期からIT化をにらんで,パソコンを導入なさっていたのですか。 | |||
| |
|||
| 野田 |
|||
| そうですね。これは私の力ではなくて,若い推進者がいないと,なかなかそういうものは進まないですね。 その牽引役は,当然,4代目になるわけですが,当社は全般的に若いスタッフが多いですから,みんなに浸透するのも早かったですね。 |
|||
| |
|||
| 西野 |
|||
| 野田社長ご自身は,建設業界にとって,これから進んでいくIT化についてはどう思われますか。 | |||
| |
|||
| 野田 |
|||
| これは,もう避けては通れないものですが,対応していくのは確かに大変だと思います。ISO取得と同様に,建設業界の中で,もっともっと進まなくてはいけないでしょうね。当社も,少なくとも業界の中で後手を踏まないように,先へ先へと推進していかなければならないと思っています。 | |||
| |
|||
| 西野 |
|||
| 協力会社さんにもIT化は浸透させていかなければならないと思うのですが,その辺に関してはいかがですか。 | |||
| |
|||
| 野田 |
|||
| 建設業の下請さんというのは,業種によっては当社よりも規模が大きくて力がある会社もあるし,その逆に,非常に小規模なところもたくさんあります。その小規模なところは,やはりパソコンよりも手書きのほうが速いと言ってきます。こんな景気の悪い時期でも,パソコン1台ぐらいは買えますよね。ただ,それを扱うことに戸惑いを感じているみたいです。会社としては,やはりそういった下請さんにも,IT化を進めてくれるように,話をしているところです。 結局,これに対応してくれないと,力のある他の下請会社が入ってきてしまうんですね。つまり,下請会社が変わってしまうということです。 |
|||
| |
|||
| 西野 |
|||
| そういう自然淘汰的なことが始まることを思うと,建設業界全体がIT化について,かなりの意識を持って臨まないといけないことになりますね。 | |||
| |
|||
| 野田 |
|||
| そうですね。大手ゼンコンは大体は進んでいるでしょうが,中堅以下はまだのところが多いように思います。全般的に言えば,まだまだこれからのような気がします。 | |||
|
|||
| 西野 |
|||
| これからはストック活用の時代などと言われていますが,リフォーム市場についてはどのようにお考えですか。 |
|||
| |
|||
| 野田 |
|||
 リフォーム市場については,当社は「オーユーリフォーム21」という別会社をつくっています。設立は8年ほど前で,まさにバブル経済がはじけた後,これからリフォーム時代が必ず来ると思い,スタートさせました。この会社は,ある大企業のフランチャイズに加盟しています。加盟した理由は,かなり営業活動がマニュアル化されていて,素人でもできますよ,という触れ込みがあったからなんです。 リフォーム市場については,当社は「オーユーリフォーム21」という別会社をつくっています。設立は8年ほど前で,まさにバブル経済がはじけた後,これからリフォーム時代が必ず来ると思い,スタートさせました。この会社は,ある大企業のフランチャイズに加盟しています。加盟した理由は,かなり営業活動がマニュアル化されていて,素人でもできますよ,という触れ込みがあったからなんです。ただ,そういう触れ込みをしていた会社には失敗例が多くて,私たちも加盟しましたが,満足にフランチャイズ等の技術や営業のノウハウなどは提供されませんでした。 そういう会社が撤退した今,リフォーム市場はどうなっているかというと,やはり放っておけない市場なわけです。現在,当社の全体的な数字を100とすると,リフォームの仕事は25%ぐらいは占め ています。 当社は元は大工ですから,私も社員も大工の発想を持っていますので,言うならば新しい御用聞きスタイルのようなことを,リフォームについて,最近,始めたところです。 |
|||
| |
|||
| 西野 |
|||
| 浅草の近辺を回られていらっしゃるんですか。 |
|||
| |
|||
| 野田 |
|||
| 月に1度ぐらい,2人1組になって回ってます。1人で飛び込みというのはなかなかできませんが,2人1組なら何とかなります。ローラー作戦と呼んでますが,こういう御用聞きスタイルを,当社のリフォームに対する1つの新しいビジネスモデルとしてアピールしていこうと思っています。 ただ,この浅草の地域の中だけでやっていくのは難しいかもしれません。やはり地場産業の景気があまり良くないし,この辺りは中小企業の商店の人が多いんですね。そうなると,例えば世田谷区,杉並区,港区とか,やはり住んでいる層が違うんですね。リフォームには,そういう市場と商売との兼ね合いが,見えない部分で意外と多いんですよ。 |
|||
| |
|||
| 西野 |
|||
| では,今後は浅草以外の地域でも,そういったスタイルで営業をしていこうとお考えですか。 |
|||
| |
|||
| 野田 |
|||
| 私の構想の中にはありますけど,それには,まず人材育成をしっかりやらないといけないでしょうね。そう考えると,まだ手を拡げてはいけない分野なのかもしれません。 |
|||
| 西野 |
|||
| 次に,昨年から施行された住宅品質確保促進法についてお伺いしたいのですが,住宅施工を手がけていらっしゃる側としては,この法律をどのように思いますか。 |
|||
| |
|||
| 野田 |
|||
| 私たちは,住宅品質確保促進法のような法律がなくても,自信を持って商売をしています。確かに,消費者からすると欲しいものなのかもしれませんが,絶対的なものかというと,それほどのものでもないように思います。ISOなどにしても,取得したのはいいけれども,実際,それを生かし切らなければ,宝の持ち腐れになるわけでしょう。 例えば建設業者に建築を頼むと,その下につく3〜4人のスタッフと共に作業に入るわけですが,このスタッフの出入りが激しくて,作業期間中に結構,変わるんですね。だからこそ,住宅品質確保促進法のような制度をつくろうというのが国の見方なのかもしれませんが,私たち建設業者からすれば,ちゃんと建設業法を通って商売をしているわけですから,これでは何のための建設業法なのか,と思ってしまいます。なぜ,さらに規制を設ける必要があるのでしょうか。 形のあるものは工場で検査して,一貫性のあるものをつくれますが,住宅を含めた建設全般については,すべての処置に均一性を持たせるのは,相当な努力が必要です。 私たちは,今までも自信を持って住宅をつくってきました。ただ,市場が住宅性能評価書のようなものを取らないといけないということになれば,それに逆らうわけにいきませんけれどもね。 |
|||
| |
|||
| 西野 |
|||
| 住宅品質確保促進法のような法律がなくても,お客様との信頼関係があればいいわけですし,それが理想の形でもありますよね。 |
|||
| |
|||
| 野田 |
|||
| そうですね。ですから,私たち地場の建設業が気をつけないといけないのは,この法律も,結局は大手住宅メーカーのほうが有利だということです。彼らは,この法律に完全に対応して,完璧に営業サイドにそれを組み込んでいます。 一方,中小建設業者の中には,わかっていても,それが実際に必要であるのかどうか,あやふやな部分,理解できていない部分があると思います。そこをしっかり理解しておかないと,営業面でマイナスになる部分が相当あるのではないでしょうか。 |
|||
| |
|||
| 西野 |
|||
| 今後,建設業界で,こんなふうに変わっていってほしいというところはありますか。 |
|||
| |
|||
| 野田 |
|||
| 今は,ただ安ければいいという風潮が強くなってきていますが,やはり建設業というのはものづくりですから,それなりにコストがかかるわけです。よく日本の建物は高いと言われますが,まず地震国であり,また建築基準法に基づいた施工方法があり,一概には高いとは言い切れないものがあるかと思います。 我々つくる側だけの問題ではなく,設計者(デザイナー)側にも,コスト面に対する工夫があってほしいと思います。 建設業の中身についても,業種が多いということが言われています。外国では,1人の職人が2〜3種類の業種をこなすので,あまり手待ちもなく,建設業の人が食えないということは,それほどないようです。 では,日本はどうかというと,昔は手に職があれば食えないなんてことはあり得なかったのですが,今は違いますよね。そういう点で,建築というものの良さを安売りせずに,もっと胸を張って,えりを正した姿勢で営業していきたいと思います。 |
|||
| |
|||
| 西野 |
|||
| 今度は野田社長ご自身についてのお話を伺いたいと思います。野田社長は3代目ということですが,小さいころから跡を継ごうと考えていらっしゃったのですか。 |
|||
| |
|||
| 野田 |
|||
| 私は長男ではないのですが,東京大空襲で兄弟を亡くしまして,親に強制された部分はありますね。 先代は祖父に跡継ぎとして育てられたみたいで,私も強くそういう指導を受けました。ですから,自分が将来何になりたいとか,考えるような暇はなかったですね。学校に行っているときからずっと現場に出て,友だちが遊んでいるようなときでも,仕事をさせられていました。 ただ,そういう経験があったからこそ今があるんだなと,年を重ねるとともに思うようになりました。 |
|||
| |
|||
| 西野 |
|||
| それは,社長業をするうえで,役に立っているということですか。 |
|||
| |
|||
| 野田 |
|||
| そうです。現場では下請さんだけでなく,他の業種の方とも一緒に仕事をしていましたので,若いときに自分の目を養ってくれる経験ができたわけです。ものづくりには,理屈ではなく,体験したことで見る目を養うということも大切ではないでしょうか。 |
|||
| |
|||
| 西野 |
|||
| 社長をやっていく上での哲学や,大事にしていることはありますか。 |
|||
| |
|||
| 野田 |
|||
| 哲学というほどのものはないのですが,人様に迷惑をかけない,人様に対して誠心誠意尽くすことをモットーに働いています。 ものづくりで一番大切なのは,やはりお客様の喜ぶ顔が見たい,という気持ちではないでしょうか。これを忘れたら,私は建設業をやめなければいけないですね。 いくら私たちが100%の仕事をしたと思っていても,お客様が気に入らなければ,それでおしまいなんです。ですから,お客様の満足した顔を見て,“こんな素晴らしいものを,この予算でよくつくってくれた”なんて言われると,ほんとうに感激しますね。 |
|||
| 西野 |
|||
| 野田社長は浅草で生まれ育ち,今も浅草でお仕事をなさっているわけですが,浅草に対しての思い入れは,かなりあるのではないですか。 |
|||
| |
|||
| 野田 |
|||
| 生まれ育った町ですから,それはもう人一倍ありますよ。当社も浅草で
100年になりますが,戦前からこの辺りにいる人は,空襲があったために,かなり少ないんですね。何しろ,本当に焼け野原になってしまって,浅草から上野駅まで見えたほどです。ですから,よく“下町の人の心”などと言いますけど,かなり希薄になってきていますね。あんまりアピールし過ぎても,嫌われてしまいますし。 そういうものは,意外と下町以外に住んでいる人のほうが感じてくれるんですね。いま浅草に住んでいる人は,ほかの地域から来た人が多いから,下町の気質とかは受け継いでいないわけです。それで,何か話し合うにしても,昔から浅草に住んでいる人間とは意見が合わずにぶつかってしまうことが,かなりあるわけです。だから,私たちは下町の人情を,もっとみんなにアピールしていかなければいけないと思っています。 また,高度成長時代に勝手なまちづくりをしてきてしまいましたから,昔の浅草のまちづくりというものを,していかないといけないと思っています。 昔の町並みはほとんど残っていないのですが,それは建築基準法からも言えるんですね。例えば,昔は木造建築だけでしたが,今は鉄筋コンクリートだったり,耐火建築方式の家しかありません。これは法律上,仕方がないことなんでしょうけど,浅草の良さを何らかの形で残そうという姿勢も無かったですね。行政からも,そういう指導はありませんでした。例えば,横浜の元町あたりは,とてもきれいじゃないですか。これからでも遅くないので,浅草らしい町づくりをしてみたいと思いますね。 |
|||
| |
|||
| 西野 |
|||
| 野田社長は非常にゴルフがお好きだということですが,ゴルフ歴はどれぐらいなんですか。 |
|||
| |
|||
| 野田 |
|||
| もう40年ぐらいになりますね。ゴルフの魅力は,どんなことも自己責任である点ですね。OBを出せば自分が悪いんだし,人に責任を押しつけるわけにもいかない。ミスが出れば,次にはいいスコアが出せるように練習して,自分を磨くこともできます。 また,ゴルフを通して友人・知人ができて,そういうつながりは,年をとってもお付き合いができますね。 |
|||
| |
|||
| 西野 |
|||
| ゴルフ以外に,何かご趣味はありますか。 |
|||
| |
|||
| 野田 |
|||
| 旅行ですね。ゴルフをやりに海外にも行きますが,それ以外にも年に何回か,家内と旅行に行きます。スケジュールが合えば,娘夫婦も一緒です。 それから,いろいろと関係している会で企画している旅行で,特色のある旅行には極力,家内と一緒に参加するようにしています。特色のあるというのは,例えばウィーンとかハンガリーとか,経済大国というよりも,非常に歴史のある国や都市を巡るツアーですね。 そういう旅行に参加して,通常,仕事上で付き合っている人と,ひと皮むけたお付き合いができるのもいいですね。 あとは,家内と銀ブラですね(笑)。若いときは勝手放題なことをやっていたけど,いつもそばにいる家内とのコミュニケーションは,年々,大事になってくるんじゃないですか。年とってから,お互いに角突き合ってても仕方ないですからね。 |
|||
| |
|||
| 西野 |
|||
| 最後になりますが,仕事でもプライベートでもどちらでも構いませんが,これからチャレンジしてみたいことは何ですか。 | |||
| |
|||
| 野田 |
|||
| いまお話したように,自分がやりたいことはやらせてもらっているから,やっぱり会社の将来のことですね。この地域の中で,だれからも認められるような会社にならないと,社員がかわいそうだからね。そういう点では,自分が元気なうちは,他社に負けないように,大きな会社というよりも,存在感の発揮できる会社にしたいですね。これも一生の仕事だと思っています。また,21世紀を迎えて当社の「第二の創業への挑戦」をスローガンとして,それを楽しみに,これからも仕事を続けていきたいですね。 | |||
