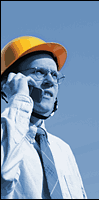  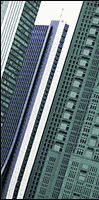 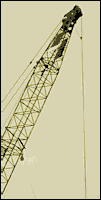  |
 |
 青木洋次郎(あおき・ようじろう) 1942年,東京都墨田区向島生まれ。 65年に日本大学理工学部建築学科卒業後,清水建設入社。67年に金子架設工業(株)に入社し,75年より同社代表取締役社長に就任,現在に至る。また,(社)日本建設躯体工事業団体連合会理事,東京建設躯体工業協同組合常任理事,日本建設工事業厚生年金基金監事,建設業労働災害防止協会東京支部中央・千代田・文京分会分会長も務める。 |
| 西野 |
|||||
|
金子架設工業さんの創業はいつごろですか。 |
|||||
| |
|||||
| 青木 |
|||||
| 当社はとび工事を基幹とした会社で,創業は明治18年になります。初代の金子兵次郎が清水建設(当時清水組)さんとご縁があり,明治22年からの長いお付き合いになります。 その後,明治から大正,昭和,平成と長い歴史の流れの中で,2代目金子卯之吉,3代目青木篤,そして4代目の私と受け継がれてきました。この間に,昭和28年から大成建設さん,昭和35年から三井建設さん,昭和41年から鹿島建設さんにお取引をいただいております。 3代目から社長の名字が「青木」になっているのは,2代目の長女,すなわち私の母ですが,一緒になった男性が「青木」という姓だったんですね。2代目には優秀な息子さんもおられたのですが,小さいころ,あまり体が丈夫ではなく,建設業には向かないということで,2代目社長は,長女の夫,つまり私の父を後継者としたわけです。 平成元年10月には,創立100周年を迎えました。その折に「金子架設工業100年史」も出版しました。内容的には元請・下請の歴史が分かり,技を誇る職人の顔もたくさん掲載され大変,良いものができたと自負しております。おかげさまで好評を博し,国会図書館や大学にも蔵書されましてね。さらにイギリスやアメリカなど,海外からも欲しいという要請がありまして,送付したほどです。 |
|||||
| |
|||||
| 西野 |
|||||
| かなり歴史がある会社でいらっしゃいますけど,金子架設工業さんの特色はどのようなところにありますか。 |
|||||
| |
|||||
| 青木 |
|||||
| 当社の特色として最初にあげるとすれば,やはり直傭制度を導入していることですね。実際,たくさんの職人さんが定着しておりまして,大変うれしく思っています。具体的には現在,とび工
223名,溶接工・鍛冶工63名,合計286名おります。さらに専属の協力会社が,とび工事会社11社,溶接鍛冶工事会社3社があり,職人数約400余名ですから,直傭と協力会社の合計で600〜700名が,毎日,100以上の現場に配置されていることになります。 会社は,生涯を託せられる企業であるという観点から,各社員に生涯プランを示すようにしています。例えば,18歳で入社して,10年後はどうなっているのか,20年後は社内でどれぐらいの位置にいるのか,役員になれるかどうか。そういう生涯プランは,会社がその規模の大小にかかわりなく考えてあげないといけないことですね。そういうコンセプトがあって,優秀な人を確保できるのだと思っています。 企業というものは,古い会社ほどやることに新しい方向を見出していかなければいけないと思いますし,そのためにも,若いフレッシュな力をどんどん入れて,ミックスしながら活性化していくことが必要です。新入社員も,10年すれば中堅社員,20年たてば立派なリーダーになるわけですから,会社の経営方針として,新卒でも中途採用でも,本気でやる気のある人を雇用するようにしています。 つまり,私の念頭には新しい型での年功序列,終身雇用制がベースにあり,会社経営があるのです。よく言われる「企業は人なり」とは,これによってでき上がってくるのではないでしょうか。 若者がどんどん入ってくるような魅力のある企業づくりをしなければいけないし,同時に古くてもいいものは残さなければいけません。古いものと新しいものをミックスしたもの,つまり温故知新の心掛けとも言うべきでしょうか。わが社の経営理念の中に,「TRADITION&INNOVATION」を掲げています。具体的には,取引先に信頼される企業づくりですね。今やグローバルな時代ですから,日本だけでなく,世界から信頼される企業づくりを目指しています。 |
|||||
| |
|||||
| 西野 |
|||||
| いま経営理念の話が出ましたが,もう少しお話を聞かせてください。 |
|||||
| |
|||||
| 青木 |
|||||
| 経営理念は「信頼される企業:技能・技術のKANEKO」です。柱は3つほどありまして,1つ目は「本業を核とした強い技能集団TRADITION&INNOVATION」です。これはいまお話したとおり,100年を超える伝統に新しいものを取り入れて,本業を核とした強い技能集団になっていこうということです。 2つ目は「安全は企業存続の生命線,今日無事」です。とび工は,高所で仕事をするなど危険を伴う作業が多く,また,後工程の方々がきちっと仕事ができるように,足場なり足元づくりをしなければなりません。それは,何もないところから組み立てていくわけですから,安全については厳し過ぎるほどに徹底した教育をしています。安全は人命尊重の崇高な精神からばかりではなく,企業の社会的責任を果たす面からも大事にしなければならないものです。まさに,企業存続の生命線というべき大事なものなのですね。日々の積み重ねが1年になります。「おはよう」という朝のあいさつに始まり,「ごくろうさん」で1日を終わろうという意味で,「今日無事」を原点としています。 そして3つ目が「人財の育成」です。普通は「人材」と書きますが,「役に立つ人物」は,会社にとってかけがえのない財産です。“材”を“財”に置き換えて「人財の育成」を経営の理念としています。 また,提案制度というものを実施しているんですよ。若手社員が普段考えている合理化や業務改善などの提案を上司を通さずに,直接社長室へ書類で提出してもらいます。これは,上司の抵抗に会わないためですけど(笑),昨春から年2回ほど実施しておりまして,相当な成果や活性化が図られています。 それから,先ほど申し上げましたように,当社のモットーは「信頼される企業:技能・技術のKANEKO」でありますが,更なる業務の拡大を図るため,業務の見直しや改革を行っておりまして,今年の11月1日よりNEW-KANEKOに転換を図り,躯体一式施工可能な総合専門工事業者を目指します。 |
|||||
|
|||||
| 西野 |
|||||
| 金子架設工業さんの職人さんは,皆さん技術力も高く,建設マスターを受彰されている方も何人かいらっしゃると聞いていますが,社内ではそういったことは,皆さんの励みにはなっていらっしゃるのでしょうか。 |
|||||
| |
|||||
| 青木 |
|||||
| 建設マスターは,国土交通省に,過去の実績をトータルに見ていただいて表彰されるわけですから,ステータスにもなりますし,当然,職人にとっても励みになります。当社には,建設マスターを受彰した者が6名おります。 そのほか労働安全マスターが2名,1級とび技能士が48名,職長教育修了者が240名,1級・2級建築士および1級・2級施工管理技士が14名います。 建設マスター受彰者を含めて,こうした資格を持っている職人には,企業として処遇・待遇面で,きちっと還元することが大切ですね。 |
|||||
| |
|||||
| 西野 |
|||||
| 建設マスターを受彰した方がいるということは,社内だけではなく,社外の方たちの信頼を得るための材料にもなりますね。それだけすばらしい職人さんがいらっしゃるのは,安全のこと以外にも,かなり徹底した教育をなさっているのですか。 | |||||
| |
|||||
| 青木 |
|||||
| 直傭制度の話をしましたが,高校や大学を卒業して入ってくる若い人たちのために,当社は認定された企業内職業訓練校を持っています。開校して,そろそろ10年になります。今年は大卒と高卒あわせて10名が4月に入校し,7月31日に4か月間の研修を終えました。入ってきたときは,「大丈夫かな?」って思いましたが,みんな立派になりました。 校長は,新入社員の親御さんに,入社式や実技研修,修了式の様子などを手紙に書いたり,当社のホームページに載せている新入社員のエッセイなどを送ったりして,現況をお知らせしています。すると,ちゃんとお母さん方もご返事をくれますね。息子のユニフォーム姿やヘルメットをかぶっている写真をみんなに見せたとか,まだ何にも仕事ができないのにお給料をいただいて,研修までしていただいたとかいうお礼の手紙をいただきました。これには,役割を全うしてくれている校長に感謝しています。 それから,毎年,会社の方針を提示しています。今年は「日々新たなり」というテーマを掲げて頑張っています。私が社長に就任したのが昭和50年2月14日なのですが,以来27年間,毎年,年頭所感を掲げてきました。この方針は,先ほどお話しました約700名の職人に周知徹底します。そのため,毎年1月に入るとすぐに2か月間ぐらいかけて,毎日のように現場での仕事が終わった後,大会議室に集まってもらっています。1回に集まるのが40〜50名ですから,10数回はやることになりますね。そのほかにも,9月から10月にかけて, 職長を対象に安全教育を徹底しています。 |
|||||
| |
|||||
| 西野 |
|||||
| そんなにやっているんですか? | |||||
| |
|||||
| 青木 |
|||||
| 徹底的にやっています。現場に行くと,詰め所に年度方針が書いてある紙を貼ってくれています。そういう形で1年間の基本的なコンセプトを,そして,最初に話しましたように,安全についても徹底して周知させます。特に,作業主任者以上にはより厳しくやっています。 | |||||
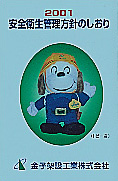 |
|||||
| 全社員に配布される「安全衛生管理方針のしおり」。中には安全衛生管理活動実施要領や年度の会社方針等が書かれている。まん中にいるのは金子架設工業のマスコット「トビー君」。 | |||||
| |
|||||
| |
|||||
| 西野 |
|||||
| 今度は専門工事業界についてお話を伺いたいのですが,業界全体がいま抱えている問題点は,どのあたりにあると思われますか。 | |||||
| |
|||||
| 青木 |
|||||
| これは私感ですが,現在は大変流動的で,不透明で,複雑であり,何が起きてもおかしくない状態だと思います。その環境の中で,元請さんと私たち専門工事業者との関連をお話いたしますと,私どものお客様というのは元請さんなんです。元請さんから仕事をいただき,また,その仕事をきっちり仕上げて,さらにご指導いただいてやっていくというのが筋なんです。 これからは公共投資も減少しますし,民間をみてもなかなか設備投資などが活発化せず,うまくいっていません。当然,公共工事と民間工事を合わせても,工事量はここ5〜6年で相当数,落ちこんでいます。それなのに,建設業者数は減少するどころか,逆に増えているんですね。競合する会社が増えるわけですから当然,分かち合えなくなります。元請さんも大変ですから,ますますコスト競争は激烈になるでしょう。 一方,私たち専門工事業者の業界をみますと,仲間の間でもよく出る不平,不満といいますか,言っても実現できないようなことがいっぱいあります。例えば,元請さんの「安値受注」や「指し値」「買い叩き」はやめてほしいとか,「支払い条件」を改善してほしいなどといったものです。当然,実現できるものとできないものがあります。 元請・下請の関係はこれからも続くわけですし,両方にとって共有のメリットもあるわけです。 今後は,ますます元請・下請の役割分担が明確になってきます。私たち専門工事業者は,「自立型の企業」を目指さなければいけません。元請さんに寄りかかる時代は,もう終わったのです。たとえ会社の規模が小さくても,自立型,自分の会社で責任をとれるような企業づくりをしていかなければ,これからの時代を生き抜くことはできないと思います。すなわち,小さくてもどこか光った会社づくりをすることです。 コスト競争が厳しくなれば,元請さんも値段を指し値で出してきます。しかし,それが安いからそれに見合った程度の仕事でいいかというと,そうではないんですね。やはり,値段が低いなら,生産性を上げてカバーする工夫をするべきです。私たち専門工事業者はプロなんですから,元請さんにどういう形でやればもっとよくなるか,意見が出せるような「提案型の企業」にならないと,これからは通用しなくなると思います。 そもそも,現代は競争の自由化,グローバル化で,コストが厳しいのは仕方がないことです。エンドユーザーも,“早く,安く,いいもの”を求めてきます。ただ,元請さんには,値段の中身を明確にして,きちっとエンドユーザーにもわかるようにしてもらわなければいけません。逆に言うと,元請・下請間での契約の中身を明確化しないと,エンドユーザーの方に迷惑がかかってしまいます。 業界の不平不満は先ほどお話したようにいろいろあります。しかし,我々にも仕事をお願いしている協力会社が何十社もありまして,やはり私たちが元請さんに対して言うのと同じことを言ってきます。結局,同じことの繰り返しなんですね。もう少し相手のことを考えて,お互いが良くなるような議論をすべきだと,最近つくづく思っています。 |
|||||
| |
|||||
| 西野 |
|||||
| そうですね。不平不満を言うだけで終わってしまったら,状況は変わらないままですよね。 | |||||
| |
|||||
| 青木 |
|||||
| そうです。お互いに言いたいことはきちっと話をして,相手の立場に立って痛みも考えてみることですね。親(元請)は子(下請)の気持ちがわからないといけないし,子も親の気持ちがわからないといけない,それが相互信頼ではないかと思います。 私が大変尊敬申し上げているあるゼネコンさんの重役さんにインタビューする機会がありました。そのとき,その方が「青木さん,1枚の契約書で買えないものがあるよね」とおっしゃるんです。1枚の契約書で買えないもの,それは何だろうか。これは,いまお話した相互信頼のことですね。ひとくちに「相互信頼」と言葉で言うのは簡単だけれども,親(元請)も我々を信じてくれる,我々も親を信じる。真からの信頼を勝ち取ることは大変なことです。 先ほど,わが社は得意先に信頼される技能集団づくりを目指しているとお話しましたが,信頼されるには,日々の努力なくしてはダメですね。先ほどの重役さんの,「1枚の契約書で買えないものがあるよね。それは相互信頼だね」という言葉は,本当に忘れられません。 さらにもう1つ忘れられない言葉があります。「いま,だれが大事か順位づけすると,一番は資本家の株主さん。これは仕方がないとして,2番目は専門工事業者と,それを囲む職人さんだね。物をつくっているのは職人さんで,うちだけでは何もできない。そして3番目がうちの社員。こういうふうに僕はいつも思っているよ」。私は,これが建設業界の原点であると,非常に感銘を受けました。 |
|||||
| 西野 |
|||||
| 今度は青木社長ご自身のことについてお伺いします。青木社長は,お仕事だけではなく,プライベートのほうでも非常に精力的で,多趣味でいらっしゃると伺っておりますが。 |
|||||
| |
|||||
| 青木 |
|||||
| それほどでもありませんが,趣味は音楽・絵画鑑賞,それに囲碁もやります。 |
|||||
| |
|||||
| 西野 |
|||||
| 幅広いですね。 |
|||||
| |
|||||
| 青木 |
|||||
| 音楽で好きなのは,ポピュラー,ジャズ,ラテン,それからカンツォーネ,クラシックもいいね。音楽は,長唄の名手だった母のDNAを大いに引き継ぎました(笑)。絵のほうは,母にも影響を受けましたが,一番影響を受けたのは父の中学時代の後輩でもある佐賀県出身の宮地亨(みやじ・とおる)画伯ですね。父の後輩といっても,宮地画伯とは私のほうが親しくしていただいたくらいです。 宮地画伯は,昭和40年代までは日本国内で活動していて,日展などにも作品を出していたのですが,50年代に入ってから,何の変化があったのか,海外に出るようになられたんです。これが良かったみたいで,フランスの二大国際展の「ル・サロン」と「サロン・ドトンヌ」で金賞をとられました。私は,宮地画伯の代表的な作品を数十点持っているんですよ。それを会社や自宅の近くのギャラリーに展示して,地域の皆さんに無料開放し,喜んでもらっています。 |
|||||
| |
|||||
| 西野 |
|||||
| かなり芸術のほうに関して,力を入れていらっしゃるんですね。 |
|||||
| |
|||||
| 青木 |
|||||
| 画家だけじゃなく,芸術を勉強している学生さんや写真家,書道家など,そういう若いすばらしい方々が,作品を展示するところがなかなかないんですね。私が住んでいるところは小さな下町ですが,町のために尽くしたいと思いまして,自宅の近くに10坪ほどの広さのギャラリーを開いています。管理は,同じ町内に住んでいる音大出身の方にお願いしています。その方の人脈もありまして,若手からベテランまで,すばらしい芸術家の方々にボランティアで作品を提供していただいております。 「下町で文化を」ということで,私のギャラリーのキャッチフレーズは,「普段着ではなく,ちょっといつもよりおしゃれをして来てください」っていうんです。名前はフランス語で「ア・ビアント」といいます。これは“See you again ”──「またお会いしましょう」ということなんでしょうね。すてきな下町の一角,風情がありまして,ギャラリーは,ちょっとしたヨーロッパ調で,中でお茶も飲めます。 また,今年はそこで季節ごとに年4回コンサートを開く計画を立てまして,春はすでに終了,夏はもうすぐ開く予定です(注:8月28日に開催しました)。もう夏休みも終わりですから,町内の子どもたちを40〜50名ぐらい招待して,新日本フィルハーモニーの,ビオラ,ヴァイオリン,チェロの三重奏に電子ピアノが入った,ミニコンサートを開きますよ。西野さん,もしお時間があれば,一度ギャラリーにお越しになりませんか。ご招待いたしますよ。 それから囲碁のほうですけど,これは父親の影響で,高校2年生のころからやっていましたね。一応,日本棋院の三段なんですよ。 最後に父と碁を打ったのは昭和49年5月でしたが,その後,父は体調を崩して入退院を繰り返し,50年2月に他界しました。それが,思い出深い一局となりました。ちなみに,父は六段の腕前でした。 |
|||||
| 西野 |
|||||
| ご家族は何人家族でいらっしゃいますか。 |
|||||
| |
|||||
| 青木 |
|||||
| 娘と息子が一人ずつおりまして,娘には子どもが2人,息子には1人います。息子は現在,清水建設さんで勉強させていただいています。 |
|||||
| |
|||||
| 西野 |
|||||
| 将来的には後継者に,とお考えですか。 | |||||
| |
|||||
| 青木 |
|||||
| 会社あっての息子であって,息子あっての会社ではございません。わが社には優秀な社員がたくさんいますから,いま敢えて申し上げることではございません。ただ,親ばかといいますか,最近見ていまして,少しは成長したかな,とも思っています。 | |||||
| |
|||||
| 西野 |
|||||
| 息子さんとは,いろいろお仕事の話をされるのですか? |
|||||
| |
|||||
| 青木 |
|||||
| それはもう,徹底的にやります。時には父親として叱り飛ばさなきゃいかんし,どなり散らしてます。最近,日本におやじがいなくなったなんて言われてるけど,私みたいなのがいてもいいんじゃないでしょうか(笑)。 |
|||||
| |
|||||
| 西野 |
|||||
| では,かなりいろいろとアドバイスなさっているのですか。 |
|||||
| |
|||||
| 青木 |
|||||
 怒るより叱ろうと思いますね。わが社は家族主義ですから,社員はもちろんのこと,協力会社の方々もすべて家族だと思っています。当然,息子もその一員としてやっていかなければならない。私も息子のことを,従業員と同じように考えています。その中で,息子が後継者たりえるかどうか,今後,自ずと決まってくるのではないでしょうか。それには,自分が努力すべきでしょうね。 怒るより叱ろうと思いますね。わが社は家族主義ですから,社員はもちろんのこと,協力会社の方々もすべて家族だと思っています。当然,息子もその一員としてやっていかなければならない。私も息子のことを,従業員と同じように考えています。その中で,息子が後継者たりえるかどうか,今後,自ずと決まってくるのではないでしょうか。それには,自分が努力すべきでしょうね。私たちの家業は,ある意味,特殊なところで,職人の世界というのはなかなか難しいところがあります。この家業に生まれ育ち,父親の後ろ姿を見て育った者が継ぐのが,本当は一番いいんです。 ですから,父親が黙っていても,その後ろ姿を見て,「親父は大変そうだな。俺が代わろう」と思ってくれるような子に育ってほしいですね。それには,痛みがわかる人間じゃないとだめなんです。そうなるためには,苦労することです。息子は大学を卒業してから数年間は銀行勤めを経験していまして,外部の厳しさも勉強しているでしょうから,いずれはうちの社員にも信頼してもらえる人間になると期待しています。 |
|||||
| |
|||||
| 西野 |
|||||
| 最後になりますが,今,お仕事以外では,どんなことに一番興味をお持ちですか。 |
|||||
| |
|||||
| 青木 |
|||||
| やっぱり孫のことかな(笑)。みんな家の近くに住んでいるので,よく遊びにくるんですよ。4歳になる孫なんか,「じーじ,一緒におふろに入らない?」なんて言うしね。帰るときにも,「また呼んでね」なんて言うものだから,もう,かわいくってね(笑)。 だから思うんだけど,子どもたちにはきれいな環境を残してあげたいですね。それにはまず,自分たちが住んでいる町,地域を良くすることですね。昔からの言葉で「向こう三軒両隣」ってあるじゃないですか。まさにこれです。出かけるときとか,お隣りに,「ちょっと留守にするから頼むよ」と声をかけるようなこと,最近はあまりないでしょ? 例えばマンションに入るならば,昔は両隣,前隣,上下ぐらいはあいさつをしましたよね。そういうことが,やはり必要ではないのかな。 それともうひとつ。私は掃除や花いじりも趣味なんですよ(笑)。これは女房と共同作業にもなりますが,休みには自宅の庭とか家の周りを掃除してます。それがどんどん近所に拡がっていった。だから,私が住んでいる町内はすごくきれいなんですよ。まだ先の話だけど,70歳になったら町会長でもさせていただいて,町の子どもたちにほうきを1本ずつ寄贈して,週に2回ぐらい町内の掃除をしたいと思ってますよ。 環境の問題も治安の問題も,各人それぞれが住んでいる町会とかで,掃除をしたり,みんなで注意をしあえば,随分,違ってくると思います。とにかく,自分の周りの身近なところをきれいにする。そういう小さな,ちょっとしたことから社会に貢献すればいいのではないでしょうか。 | |||||
金子架設工業(株)ホームページ http://www.kanekokasetsu.co.jp/
