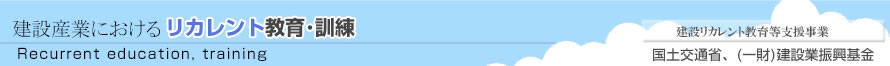事例03
仮想の技能訓練が行える、ICT |
|
|||||||
VR技術等を用いた建設リカレント教育を試行する事業連携体(東京都) |
||||||||
・ICT土工研修において、運営経費の軽減や実習時間の増加を図るため、実機を使わずICT建機の技能訓練が行える環境を構築。 |
||||||||
訓練用ICT建機の手配費用が研修運営上のネックに |
||||||||
(一社)日本機械土工協会は、職業能力開発校である富士教育訓練センターを運営する職業訓練法人全国建設産業教育訓練協会との連携により、「i-Construction標準教育のモデルカリキュラム」を構築。これにもとづくICT土工研修を、富士教育訓練センターや関東地方の建設業協会において、平成28年3月の試行を皮切りに順次実施している。受講者は約2年間で延べ80名を超え、実施の成果は確実に広がりつつある。 |
||||||||
VR、AR、MR等の技術を用い実習用コンテンツを試作 |
||||||||
こうした状況を鑑み、 (一社)日本機械土工協会を事業管理者とする連携体は、ICT建機の操作実習においてスケジュール上の制約を少なくし、実習時間の増加を図るため、実機による訓練を補完する操作実習用コンテンツの開発・導入を決め、その試作に取りかかった。 |
||||||||
技術の進化を的確に捉えたバージョンアップが課題 |
||||||||
ICT建機の操作実習用コンテンツの基本設計は、(一社)日本機械土工協会の労働安全委員会の監修のもと、同協会の会員である機械土工の専門工事会社に加え、協会外からもゼネコン、建機メーカー、および建機レンタル会社など数社から技術支援を受けて進めている。また、コンテンツ(3Dモデルデータ)を表示する、「ホログラフィック処理装置」には、既存の製品を使用することとしている。 |
||||||||