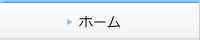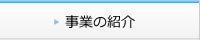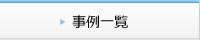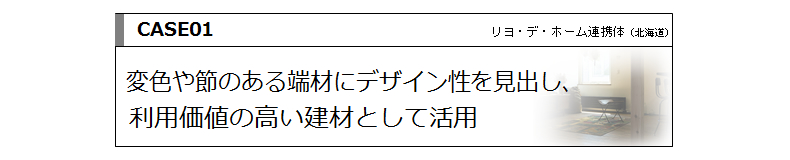
| 連携体名 | リヨ・デ・ホーム連携体 | 事業管理者名 | (株)リヨ・デ・ホーム |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市 | 構成員 | (有)工作創庫 |

■見栄えの悪さにより敬遠される端材の、建材としての有効活用に取り組む
住宅建築に使われる材木は、仕上がりの美しさの点から、一般に変色部分があるもの、節(ふし)があるものは使用を敬遠される。そのため、原木を材木に加工するときに出る“見栄えの悪い”部分は、利用価値のない「端材」として扱われる。端材は、一部はバイオマス燃料として活用されるケースもあるが、多くは使い道のないまま放置されたり、廃棄されたりしている。こうした状況をもったいないと考え、建材としての端材の可能性を見出そうとしているのが、札幌市を拠点に注文住宅の設計・施工を手掛ける(株)リヨ・デ・ホームである。
変色部分や節を“模様”だと考えればむしろ端材の利用価値は高い、というのが同社の考えである。長野県の建材メーカーから、「アオ」と呼ばれるアザのような変色部分や節のある信州松の端材を、どのように活用できるかと相談を受けた際、同社は模様を活かして洋風建築に使用してはどうかとアドバイスしている。平成28年には、札幌市内に信州松の「アオ材」を使用した洋風建築のモデルハウスを設置するなど、端材活用の取組みを進めつつある。
■変色部分や節を切り取らずそのまま利用、木材の廃棄を少なくし加工の手間も低減
変色部分や節がある部分を切り取ることなく、そのまま利用することができれば、木材の廃棄を少なくできるうえ、加工の手間も減らせるため、コストダウンと同時に生産性の向上にも寄与する。その確信のもと、(株)リヨ・デ・ホームは、建材としての端材の有効利用をさらに推し進めていくことを決意した。
幸い、同社にはこれまで培ってきた本州の会社との幅広い関係を活かして、独自商品(建材)を開発してきたという強みがある。デザイン開発力認められ、商品開発を任される形で様々な仕事を手掛けきた。この実績を足掛かりに、同社はこれまで使われてこなかった端材を、デザイン性の高いフロアー材、壁材、窓材として活用する検討に取り組むこととした。
同社はブランド化やデザイン等に関してアドバイスや協力を得るため、札幌市のクリエイター集団である(有)工作創庫と連携。ステップアップ支援のもと、平成29年度から31年度までの3か年計画(戦略編、事業推進編)の策定や、事業の内容・進め方を協議、確認する「松の端材活用開発会議」の開催など、具体的な取組みを開始した。
■低価格と優れたデザイン性で、期待される市場での競争優位
連携体では、端材を活用した材木について、従来の商品に比べて価格を3割程度安くできると見ており、デザイン性が優れていれば市場での競争優位を築けると期待している。商品化が実現した暁には、建材商社を通じて全国の工務店に供給し、あわせて“ブランドの家づくり”の企画販売を行っていくことも予定している。
また、連携体では、今回取り組む事業スキームを、端材の扱いに苦慮する全国の事業者に向けて水平展開し、情報やノウハウの共有を図っていきたいと考えている。
■試作品の出展やモデルハウスの建築で、顧客のニーズを探り方向性を検討
端材を活用した材木の検討と開発は、長野県の建材メーカーの工場で行った。平成29年12月に信州松の「アオ材」を使用した試作品が完成し、翌年3月に東京で開催された、「第24回 建築・建材展2018」で公開した。また、壁材にするのならデザイン性があると考え、穴のあいた部分を使った材木の試作も進めている。
また、既設のものに加え、さらに2棟のモデルハウスを増設することにも取り組んだ。ふんだんにアオ材を活用したこれらのモデルハウスの建築は、札幌市内と江別市内で進められ、それぞれ平成30年の2月、3月に竣工した。
連携体は、これらの取組みに対する顧客や取引先の評価や反応を通じてニーズを探り、それをデザイン性やコストダウン等について、今後の方向性の検討材料にしたいと考えている。そこで、今年度は経営コンサルタント会社に委託してモデルハウス訪問客、および取引先企対象に、ほぼ同じ内容の設問でアンケート調査を実施。回答者の意見、要望について集計・分析を行った。
■歩留りのよい加工方法の検討など、生産性向上を軸に商品供給の環境を整備
開発した商品を供給していくための、環境整備にも取り組んだ。 (株)リヨ・デ・ホームは、施工する際、パターン化して施工できるよう、職人向けの図面を用意した。また、この図面で施工するための材木を生産する際は、どのような長さ・幅にすれば最も効率よく部材がとれるのか、すなわち最も簡単、かつ最も廃棄する部分を少なくできるのかということについて、建材メーカーと検討・打合せを行い、それを踏まえて生産・出荷の体制を構築した。
販売面については、前述の通り、モデルハウスなどにより顧客に直接訴求し、評価してもらう戦略を立てている。また、業界向けにも、全国工務店協会における工務店向けの講演会など、様々な機会を通じて宣伝していく予定である。これらの具体的な取組みとして、今年度は端材を取り入れた住宅のPRパンフレット2,000部の作成と配布、札幌市内の会場に業界関係者90名を集めての、PRセミナーなどを実施した。他にSNSを活用した商品情報の発信にも、積極的に取り組んでいる。
■本州の企業との交流や視察を進め、様々な商品の検討・開発に取り組む
今後、連携体は本州の企業との交流や新しいデザインの視察などを進め、北海道産カラマツの端材を活用した材木など、様々な商品を検討し、開発していきたいと考えている。そこで今年度は、長野県の建材商社、建材メーカーを訪問。端材活用についてのプレゼンテーションや意見交換、製材工場視察などを行っている。
今回の取組みは、リサイクル社会の形成を背景に、端材の有効活用により生産性の向上に貢献する取組みとして、モデルとなり得る汎用性を備えている。だが、端材を活用した材木は、これまでほぼ存在しなかった商品だけに、どれだけ受け入れられるのかは未知数である。そこで連携体は、アンケート調査の結果を踏まえた顧客や取引先のニーズのフィードバックや、和風建築への用途拡大などに特に力を注ぎ、端材を活用した住宅建築が普及していく環境を整えたいと考えている。
●新たな材木の市場展開に向けて、職人がパターン化して施工できる図面の作成、歩留りよく製材できる方法の検討など、生産性を向上させる環境整備に取り組んだ。