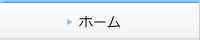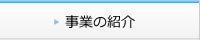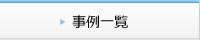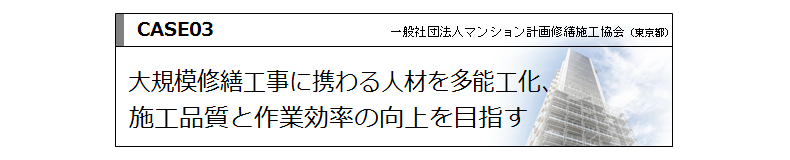
| 連携体名 | (一社)マンション計画修繕施工協会 | 事業管理者名 | (一社)マンション計画修繕施工協会 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 | 正会員数 | 151社 |

■増加が続くマンションの供給戸数、改修工事の需要も拡大
マンションの供給戸数は年々増加の一途を辿っている。国土交通省の「平成28年度住宅経済関連データ」によると、平成28年末時点において全国で約633.5万戸が供給されており、平成18年末時点の供給戸数、約485万戸と比べ、10年間でおよそ1.3倍の増加となっている。こうした状況を背景に、マンションの居住環境を適切に維持・保全するために欠かせない、計画的な改修工事の需要も拡大しつつある。
こうした状況を受けて、管理組合など発注者から信頼される、良質な改修体制を確立すべく、マンションの改修工事に携わる専門業者の業界横断的な団体として、平成20年12月、(一社)マンション計画修繕施工協会(以下「協会」)が設立された。平成30年1月時点の、協会の会員企業数は153社。塗装、防水、下地補修、管工事などを手掛ける企業が、広く全国各地から参加している。
■各種の専門工事業者が絡む大規模修繕工事、その品質と作業効率を多能工が向上させる
協会が業界横断的に組織されていることからもわかる通り、マンションの大規模修繕工事には、各種の専門工事業者が絡んでいる。
マンションの大規模修繕工事は(1)外壁の躯体補修工事、(2)シーリング工事、(3)塗装工事、(4)防水工事の順番で施工される。この流れの中で、前の工種を担当する技能工が後の工種のことを知らずに施工すると、その連携の悪さから品質に影響が及ぶことになる。例えば、下地補修工がきれいな状態にしないと、塗装工はきれいに仕上げることが出来ない。また、下地補修工や塗装工が塗料等を床に落としたままであると、防水工がきれいに仕上げることができないこともある。こうしたことから、マンションの大規模修繕工事では、同一の現場に携わる業者間で、各工程間のつながりを意識した品質管理が重要であり、その担い手として期待されるのが、1人で複数の作業を遂行できる技能を身に付けた多能工である。
現場に多能工を従事させることができれば、工程間のつながりを理解していることによる品質の向上と同時に、1人で複数の工程に従事することも可能であることから、作業効率の向上も図ることができる。このことは、建設現場の担い手不足が問題となっている中、その解決を図る有効策の一つとして期待される。
■改修工事に特化した育成プログラムを確立、技能工の多能工化に取り組む
こうした背景から、協会は改修工事に携わる多能工の育成に取り組むことを決めた。しかし、現在行われている建設技能工育成の取組みは、大半が「新築」を前提としたものである。それにより得られた知識、技能だけでは、マンションの大規模修繕工事においては、対応しきれない工事が少なくない。
そこで協会は、改修工事に特化した技能工育成プログラムを確立し、そのうえで防水改修工、シーリング改修工、塗装改修工などそれぞれの改修技能工に、複数の技能を身に付けさせるという方針で取組みに着手した。
■つながりのある4つの工種を選定し、毎年度1工種ずつ足かけ4年の研修を実施
多能工育成の取組みは、改修工事に特有の工種から、4つの工種を選定して研修を実施することとし、平成27年度から始まった。
4つの工種は、とび、サッシの改修など、かなりの専門性を要するものはあえて外し、ある程度の経験を積めばできそうなもので、かつ工程間のつながりがあるものが選定された。平成27年度は躯体改修工事、平成28年度は防水改修工事と、各年度1つの工種について育成プログラムが構築、実施され、平成29年度はシーリング改修工事についての研修が行われた。取組み最終年度となる平成30年度は、塗装改修工事についての研修が実施される予定である。
■研修受講者の多くが未知の作業を体験、多能工に向け有意義な第一歩を踏み出す
平成29年度の、シーリング改修工事についての研修は、静岡県富士宮市にある富士教育訓練センター(キーワード解説)で、9月上旬に3泊4日の日程で実施された。主に協会の会員各社の協力企業から、20歳~30歳代と比較的若い世代を中心に、12名の技能工が参加した。
富士教育訓練センターには、新築工事に関する講師は数多くいるが、改修工事を教えられる講師はいない。そこで研修は、講師及びカリキュラムを協会がセットで提供して実施した。カリキュラムの内容については、どのような資材が必要なのかを検証しながらその完成に努めた。また、研修で使用するテキストは、協会がこれまで多数作成してきた維持修繕に関する書籍から抜粋して、オリジナルのものを作成した。
研修は座学のほか、富士教育訓練センター内にある改築中の古い建物の一部を利用し、改修工事の実地講習を行った。今まで刷毛しか持ったことのなかった塗装工が、初めて鏝を使って樹脂モルタルを塗りつける体験をしたなど、多くの受講者にとって研修内容は全く未知のものであった。それだけに自分が担当する前後の工程を、「こうやるのか」と、身をもって体験できたことは、これから多能工を目指そうとしている技能工たちにとって、有意義な第一歩になったと思われる。すでに初年度から研修に参加してきた技能工が、一人で躯体、防水、塗装の工事に対応できることから、現場で重宝がられているという成果も上がっている。
■今後は改修工事を教えられる講師の養成や、中級・上級コース開講などが検討課題に
今後、協会は4つの工種の育成プログラムを、「マンション計画修繕多能工育成プログラム」として全国展開し、各工種のプログラムをブラッシュアップしながら、定期開催していきたいと考えている。この目標の実現に向け、実施体制に関しては、改修工事を教えられる講師の養成、各地の研修施設等との連携、研修用資機材の常備などが、また、実施内容に関しては、今回実施したカリキュラムを初級コースと位置づけた中級・上級コースの開講、フォローアップ研修の実施などが検討課題となりそうである。
![]() 富士教育訓練センター
富士教育訓練センター
建設技術者・技能者の教育訓練を目的に、職業訓練法人全国建設産業教育訓練協会が運営する施設。認定職業訓練による職業能力開発校である。平成9年(1997年)4月に開校した。
●近年需要が高まりつつあるリフォーム・改修工事は、「新築」が前提の知識、技能では十分な対応ができないケースが少なくない。そこで、「改修」に特化した技能工育成プログラムを確立した。