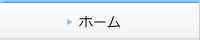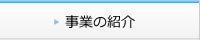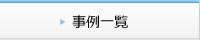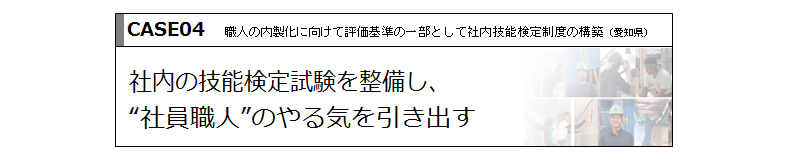
| 連携体名 | 職人の内製化に向けて評価基準の 一部として社内技能検定制度の構築 |
事業管理者名 | (株)ヤマガタヤ |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市 | 構成員 | (有)スペースタナカ |

■確保可能な職人の減少が続く見通しに、新たな担い手の育成が急務に
近年、多くの産業分野において叫ばれている人材不足は、建設業においても例外ではない。平成28年平均の建設業就業者数は、約492万人で、ピーク時(平成9年平均)の約685万人と比べ、28%も減少している。
名古屋市に本社を置き、建材や住宅設備機器の卸売と、専門工事業者として内装・外装工事、リフォーム、建築工事などを手掛ける(株)ヤマガタヤは、そうした人材不足の状況に危機感を覚え、平成28年に現状を認識し将来を予測しようと調査を行った。その結果、常時外注している協力会社の職人、約130名が、10年後には推計で97名と、ほぼ4分の3まで減少するとの見通しが明らかとなった。同社では最近工事部門の事業拡大が進み、職人を使う機会が増えつつある。それにも関わらず、今後確保できる職人が減っていくという見通しに、新たな担い手の育成が経営上の急務となっている状況が、あらためて浮き彫りとなった。
■自社の社員を職人として育成、工事の安定受注や他社との差別化を図る
ところが、担い手を育成するといっても、(株)ヤマガタヤの協力会社の多くには若者が常時入職してくる状況はなく、厳しい経営環境の中、人材育成の余裕もないのが実情である。こうした状況も踏まえ、 同社は自社の社員を職人として育てる、“職人の内製化”に、平成25年から取り組んでいる。職人を内製化することで、安定的に工事を受注することができ、また「社員職人」のスキルアップを図ることで品質、納期、価格面において、他社との差別化が可能になるものと期待している。
職人内製化の取組みは、当初、職人数の減少割合が大きいと予想される職種から、1職種ずつ育成していく計画でスタートしたが、その後多能工の育成を目指すこととなり、計画は若干変更されている。方針転換の背景としては、社員職人が多能工となれば、工程が組みやすく、現場に入る職人の数を減らせるなど、効率化とコストダウンが進み、会社にとってのメリットが大きいことがあげられる。手掛ける事業領域の幅広さからも、多能工化は同社にとってふさわしい取組みである。
■やりがいを感じて仕事に打ち込めるよう、教育・人事評価の両制度を整備・確立
職人の内製化を進めた結果、(株)ヤマガタヤでは全社員150名の1割にあたる15名が、大工など現場での施工ができる社員職人として育ち(平成30年2月現在)、期待した成果が着実に上がりつつある。
この状況を踏まえ、同社は、職人の内製化をより効果のあるものとすべく、新たな取組みに着手した。その内容は、育成した社員職人がモチベーションを維持し、やりがいを感じて仕事に打ち込めるよう、職人の教育制度、人事評価制度を整備・確立する、というものである。この計画に、同社の協力業者で、同じような人材育成上の悩みを抱える内装工事業者の(有)スペースタナカ(岐阜県羽島市)が賛同し、この取組みは2社の連携により進められた。
■社員職人の育成にチューター制度を導入、自由に選択できるキャリアパスも設定
事業のうち、職人の教育制度を整備・確立する取組みとして、(株)ヤマガタヤは平成29年7月、工事営業部門の下に「施工部」を設立する組織体制の変更を行った。施工部には、それまで各営業所に所属していた職人が集められ、職種ごとに「面倒見役」を配置。若手社員をベテラン社員との縦の連携の中で社員職人として育てていく、チューター制度が導入された。
また、高校や専門学校を卒業し、職人を希望する若手社員に対し、職業人としての自分の進路が具体的にイメージできるよう、19歳から60歳までのキャリアパス(キーワード解説)を設定。社員としてキャリアを全うするケース、独立する道など、本人の希望に合わせてできる限り自由に選択できる仕組みを用意した。
これらの制度のもと、同社は概ね5年の修業期間を目安に、若手を一人前の社員職人へ育てていく考えである。さらに、一人前になった職人を、新たな「面倒見役」として若手社員の育成にあたらせ、これまで進めてきた“職人の内製化”の取組みを、名実ともに完成させたいと考えている。
■モチベーションと技能の向上を目的に、自社独自の技能検定制度を構築
次に、職人の人事評価制度については、個人の目標を設定し、その達成度を評価する「目標管理シート」と、親方、面倒見役、そして本人が、挨拶、モチベーションの有無、困難に直面した時それに立ち向かう姿勢など、様々な面を評価する「評価シート」を導入した。さらに、職人のモチベーションアップと技能向上を目的に、独自の技能検定制度を構築した。
今年度の社内技能検定試験は、平成30年1月に実施。連携体両社の入社2~5年目の職人8名がボード仕上げ、クロス貼りなどの実技課題に取り組んだ。なお、実技課題は、(有)スペースタナカをはじめ、各職種の親方に協力を仰ぎ、実際の作業の中で注力すべきポイント等を聞きながら(株)ヤマガタヤが作成した。
検定試験の結果は、検定委員(社員および社外職人)が減点法により評価し、それを技能成績書として受験者に通知した。この評価は合格・不合格の判定をするものではなく、できない点を親方や世話役がフォローする際の参考として、また本人が「去年よりもどれだけできるようになったのか?」を知るバロメーターとして活用することとした。
■会社による成長度合いの見守りが、若手社員の離職防止につながるとも期待
社内技能検定制度は、一人前の職人として育つまで、成長の度合いを会社がしっかりと見守っている、ということを若手社員に意識させ、離職を防止する取組みとしても期待されている。
連携体の2社は、引き続き社員職人にやる気になってもらえることを目標の中心に据え、今年度の状況を踏まえて課題の内容、実施時期、対象者の年次、対象人数などについて検討を加え、制度の充実を図っていく考えである。
![]() キャリアパス
キャリアパス
企業の人材育成制度の中で、どのような職務にどのような立場で携わるか、またそこに到達するために、どのような経験を積みどのようなスキルを身につけるか、といった道筋のこと。
●若手が一人前の社員職人に育っていく過程で、本人、会社のいずれもが成長の度合いを客観的に確認できるよう、自社独自の技能検定制度を構築した。