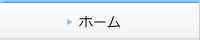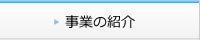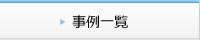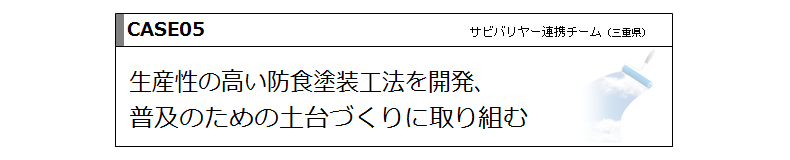
| 連携体名 | サビバリヤー連携チーム | 事業管理者名 | (株)エコクリーン |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 三重県松阪市 | 構成員 | 大進産業(株) |

■鋼構造物の長寿命化に寄与する、防食塗装工法を全国展開
三重県松阪市の(株)エコクリーンは、さび転換型防食塗装工法、「エポガードシステム」の全国展開に力を入れている。
エポガードシステムは、鋼構造物の長寿命化を目的に開発された下塗塗装技術であり、NETIS(新技術情報提供システム)にも登録されている。その基本的な原理は、高浸透性の下地処理剤と、さび転換型特殊エポキシ樹脂系下塗り剤の相乗効果により、素地調整の際に電動工具や手工具では除去しきれない赤さびを、マグネタイトという安定した物質(黒さび)へ化学的に転換させ、赤さびを内部から無力化。長期にわたり防食性を維持するというものである。3種ケレン(手工具と電動工具を併用し旧塗膜を落とす作業)程度で素地調整後の鋼構造物に対しても施工でき、しかも従来工法に比べ低コストであるという特長が注目されて、近年鋼製橋梁の塗り替え工事等での採用が増えている。(株)エコクリーンがこの技術の本格的な営業を開始してから10年目となる平成30年2月までに、全国でおよそ1,250件の施工実績がある。
■既存の技術をバージョンアップし、生産性の高い新たな技術を開発
このように、インフラの長寿命化という社会的要請が高まる中、普及が進んだエポガードシステムだが、(株)エコクリーンは、更なる工期短縮や経費削減を実現しようと、新たな技術の開発に取り組んだ。その結果誕生したのが、エポガードシステムをバージョンアップした技術、「サビバリヤー」である。
サビバリヤーは、エポガードシステムで必要であった下地処理剤を用いなくとも、新開発の下塗り剤のみでも黒錆転換の化学反応を十分に起こすことができる。これにより、エポガードシステムで施工する際に必要な脱脂洗浄、下地処理、下塗りの3工程のうち、下地処理が不要となり、2つの工程で施工が完了する。また、脱脂洗浄で用いる洗浄剤を、エポガードシステムで用いるものに比べ更に洗浄力の高いものに改良し、洗浄剤の使用量を減少することを実現。結果、洗浄剤の費用も抑えられる。このように、従来の技術と比べ、工期の短縮とライフサイクルコスト(キーワード解説)の低減を実現したことが、サビバリヤーの大きな特長である。
■新たな防食塗装工法の確立で期待される、橋梁補修工事の全国的な生産性向上
建設後50年以上を経過した鋼製橋梁の割合が年々高まっていることから、今後その補修需要も増加していくことは確実である。新たな防食塗装工法の技術が確立し、普及すれば、橋梁補修工事の全国的な生産性向上に大きく貢献するものと期待される。
サビバリヤーの技術を確立し、普及させるためには、取り組むべき課題が2つある。1つは、この技術で用いるため新たに開発された、防食塗料の性能評価を確立することである。そしてもう1つは、施工業者に防食塗料や施工方法についての知識と技術を習得してもらうことである。この技術による塗り替え工事では、防食効果をより一層高めるため、表面洗浄、素地調整、膜厚測定等の正確な実施が特に重要である。そのため、講習等を通じた施工基準の明確化が、欠かすことのできない取組みとなる。
■従来工法との比較ができるよう、各種性能評価試験を実施
課題への取組みは、(株)エコクリーンと、エポガードシステムでの鋼構造物の防食塗装を手掛けている、栃木県宇都宮市の大進産業(株)の連携により進められた。大進産業(株)は、主に講習会による知識・技術の普及を担当した。
防食塗料の性能評価については、経年で30年後の劣化状況を予測するため、(一財)日本塗料検査協会に依頼し、塗料の付着性を評価する付着性試験(プルオフ法)、防食性を評価する複合サイクル試験、キャス試験、屋外暴露試験を実施した。『鋼道路橋防食便覧』(公益社団法人日本道路協会)に、「新技術を使う場合には、十分に熟知された技術と比較すること。」とあることから、今回の試験では、サビバリヤーの試験体と従来工法の試験体を用いて、比較試験を行った。試験の結果は、今後報告書として取りまとめられ、発注者や設計者への説明資料など、新工法のメリットを理解してもらうためのツールとして活用される予定である。
■施工レベルが一定水準に保たれるよう、施工業者向け講習会の内容や体制を検討
施工業者向けの講習会は、施工業者が工事を落札しサビバリヤーを用いることにならないと受講依頼がないため、現時点ではエポガードシステムの講習会の場を利用して、その優位性を伝えながら、サビバリヤーについての説明を行っている。
連携体では、今後サビバリヤーについての講習を本格的に実施する際には、現在エポガードシステムについて行っているのと同様に、座学と実地からなる講習会を行う計画である。塗装業者の中には、自己流の作業を行う業者や、基本を忘れている業者もいる。そこで連携体は、業者間で施工の技術レベルが一定水準に保たれるよう、座学では「塗装の基礎」「錆転換工法の施工とメカニズム」等の講義を、また実地では実際に鉄板を使い、材料に触れ、塗料の粘度や塗り具合等を体感する講義を取り入れるなど、講習の内容や体制について検討と準備を進めている。
なお、2つの課題への取組みのほか、技術の普及、販路開拓に向けた足掛かりとするため、名古屋市で開催された「建設技術フェア2017in中部」をはじめとする3つの展示会への出展、業界専門紙への広告出稿を行った。
■
今後は評価と実績を築くことが主要課題、広い視点からの知識普及などを検討
今回の取組みは、生産性の高い防食塗装工法を普及させていくための、土台づくりとして位置づけられる。その土台の上に、いかにして評価と実績を築いていくかが、連携体にとって今後の大きな取組み課題となる。
そこで、連携体では防食塗料の性能評価試験について、今後10年・20年・30年と長期間継続して行い、実際の環境での実証も進めていきたいと考えている。講習会においては、サビバリヤーだけではなく足場工や使用工具、有害物質対策等も含め、鋼製橋梁の長寿命化について、広い視点から知識を広めたいと考えている。
![]() ライフサイクルコスト
ライフサイクルコスト
製品や構造物などの費用を、調達・製造~使用~廃棄の各段階で必要な経費の合計額で考えたもの。「生涯費用」ともよばれ、英語(Life cycle cost)の頭文字から、LCCと略されることもある。
●性能評価のための試験には、従来技術との比較を取り入れ、新たな技術を普及させていく際、その特徴や優位性を明確に示すデータが得られるようにした。