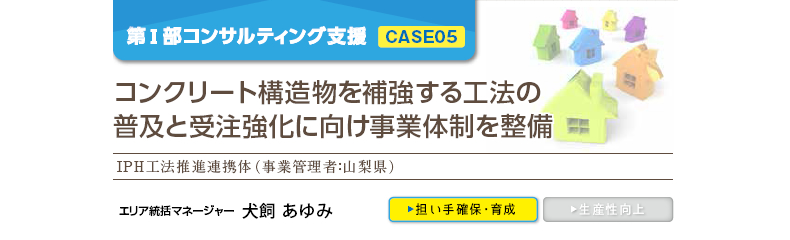
| 連携体名 | IPH工法推進連携体 | 事業管理者名 | I社 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山梨県 | 構成員 | N社 |
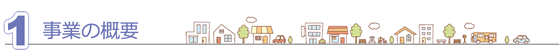
■コンクリート構造物の長寿命化に寄与し、活用の拡大が期待されるIPH工法
IPH工法(内圧充填接合補強工法)は、傷んだコンクリート構造物の耐力を回復させ、その長寿命化に大きく寄与する技術である。
大規模改修でも莫大な費用を伴わないコンクリート構造物の補修方法としては、「自動式低圧樹脂注入工法」が多く用いられている。しかし、この工法は躯体内部に雨水が浸入しないように表面のクラックを塞ぐことを目的としており、注入した樹脂はコンクリート内部構造にまでは達しない。これに対し、IPH工法は、穿孔した穴の内部から樹脂を注入し、コンクリート躯体内で放射状に拡散させることにより、末端の微細クラックまで充填することができる。
このような特長から、IPH工法は鉄筋とコンクリートの付着強度を高めるだけではなく、高い防錆効果も得られる唯一の高密度充填工法として、土木学会の技術評価を得ている。また、NETISにも登録され、工法特許も取得している。土木分野では、今後、橋梁等の維持補修における、IPH工法の活用の拡大が期待されている。
■IPH工法の普及と受注の強化を、今後の営業戦略の重点課題に位置付け
この工法については、その普及・発展を目的に、(一社)IPH工法協会(以下「協会」)が組織されており、I社は協会に所属する、老舗の建設企業である。I社は、長年にわたって地域のインフラを支え続けてきたが、地元の工事が減少しているため、業務エリアを拡大し東京都内で受注を確保することを目指していた。その突破口となるのが、コンクリート構造物の長寿命化に寄与するIPH工法であると考えており、IPH工法の普及と受注の強化を、今後の営業戦略における重点課題と位置付けていた。
だが、I社にはIPH工法に対応できる人材が少なく、施工実績も乏しい。IPH工法による収益確保の取り組みを独自に進めていくことは、I社にとって大きな負担となることが予想された。
そこで、I社は、同じく協会の会員企業で、IPH工法を新たな収益の柱にしたいと考えていたN社と連携。コンサルティング支援のもと、IPH工法の普及・受注によって利益を確保する方策の、検討と実行に着手した。
■工法の普及・改良、人材育成に取り組み、利益を出せる事業体制づくりを進める
IPH工法は、従来工法に比べ、ライフサイクルコストが約30%低減することが証明されている。だが、穿孔作業の手間がかかり、樹脂の注入量が増えるため、初期コストは割高となる。従来工法との競争もあり、現状以上の価格アップは難しいため、利益確保のためには施工面での習熟・効率化等によるコストダウンが必要である。また、工法の普及に向けては、技術者等の育成が重要となる。協会では、管理面のほか、施工面についても資格を設けるなど、資格制度の充実が図られている。連携体ではそうした点を踏まえ、ノウハウ等を共有しながら、工法の普及活動のほか、工期の短縮、原価低減につながる施策の検討、及び技術者・技能者の育成などに取り組み、IPH工法によって利益を確保できる事業体制づくりを進めた。
■公共工事で採用してもらうため、工法の良さをアピールするツールを作成
まず、IPH工法の普及を図るため、連携体は、他の協会会員の参加も得たうえで、ミーティングを重ねながら、IPH工法を公共工事で採用してもらうための営業施策を検討した。その一つが、IPH工法の良さをアピールするツールの作成である。具体的にはメンテナンスが不要でライフサイクルコストで約30%低減できること、及びコンクリート自体を健全にするという性能を持つことの、2つのメリットを強調する営業ツールの作成に取り組んだ。これまでは、施工した部分がコンクリート内に入ってしまい目視ができないため、優位性の説明をすることが難しかったが、電磁波を使って性能を“見える化”(キーワード解説)するなど、訴求力を高める工夫を行った。
また、東北地方や名古屋、広島地区では、IPH工法を活用した事例が比較的多く、これらの事例についての勉強会も実施した。連携体は、今後これら他地域での事例を整理し、工法のアピールポイントを説明できるようにすることで、引き続き東京都内を主要ターゲットとした、IPH工法の普及に取り組んでいくこととしている。
なお、事業管理者のI社では、これまでIPH工法に関する営業を、東京の委託社員を中心に行っていたが、今後の営業戦略における重要性を鑑み、①営業力強化および協会への働きかけ強化のため、社長がより直接的に関与する、②推進担当者として正社員(営業)を担当者として配置するなどの、営業体制の見直しを行った。
■技術系社員の約8割が講習に参加し、協会資格の取得に至る
次に、IPH工法の施工体制の整備、及び従業員の教育に取り組んだ。協会には、連携体の2社のような技術系会員(工事の管理を担う)と、施工会員(実際の施工を担う)とが存在する。東京都内では、これまでIPH工法による工事実績が少ないことから、施工会員の育成が課題となっていた。そこで、連携体は施工を担当する業者を両社共通とすることで、施工会員の育成と作業の標準化について、ノウハウの共有を図った。
また、IPH工法による工事実績の多い、他地域の協会会員による講習会の実施や、工事視察等により、今後、東京都内でIPH工法が普及した際の、施工体制の整備を行った。
技術者の育成については、連携体2社の技術系社員が、技術講習等に参加した。特に、事業管理者のI 社では、これまでI PH工法による工事は社内の特定の人だけが関与している特殊な工事で、社内全体としての関心が薄かった。だが、今回の取り組みにおいて技術系社員の約8割が講習に参加し、協会資格の取得に至った。
■
営業面・施工面の両面において、今後の普及に向けた体制が整う
今回の取り組みによって、I社、N社ともに平成28年度中にIPH工法による工事での受注目標を達成することはできなかったものの、営業面・施工面の両面において、今後のIPH工法の普及に向けた体制を整えることができた。連携体は、引き続き受注目標額の達成を目指し、東京都内の案件を主要ターゲットとして、営業活動を強化していく考えである。
![]() 見える化
見える化
製造現場や企業経営における管理方法の一つ。業務の状況を映像・グラフ・図表・数値などによって誰にでも分かるように表すことで、問題が発生しにくい環境、問題が発生してもすぐに解決できる環境を整える取り組みである。
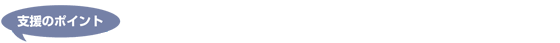
●技術系社員の大多数が講習に参加し資格を取得したことで、IPH 工法の普及は一部の社員だけが関与する取り組みではなく、会社全体で取り組むべきものという意識が社内に浸透した。また、一社単独ではなく連携体として取り組むことで、効果的な下請(施工)業者の育成が可能となった。