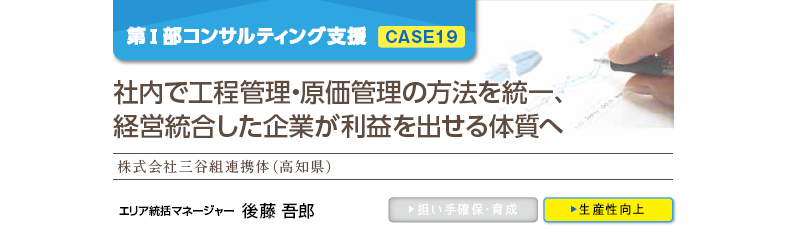
| 連携体名 | 株式会社三谷組連携体 | 事業管理者名 | (株)三谷組 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 高知県高知市 | 構成員 | (株)オアシス・イラボレーション |
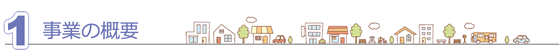
■複数の建設企業が経営統合したため、異なる工程管理手法が社内に混在
高知市に本社を置き、官公庁工事を中心に事業を展開する総合建設業者、(株)三谷組は、地域・業種が異なる複数の高知県内の建設企業が、数年前に経営統合してできた会社である。
同社は近年受注額が増加傾向にあるものの複数の企業のバックボーンが背景にあるため、社内では旧所属の会社ごとに工程管理の手法、原価管理の実務や進め方が共存していた。
そのため、実施工程表が大まか過ぎて進捗状況と実行予算(キーワード解説)との対比ができないなど、生産性向上を進める上でネックとなっていた。また、作業の遅れや、何か問題が発生しても、その原因を究明に手間取ることがあった。
■生産性の向上を目指し、工程管理、原価管理の方法の統一を図る
以上のような状況から、(株)三谷組における現場の生産性は一定であり、受注額に見合った利益率を確保できない状況が続いていた。
そこで、十分な利益を確保できる経営体質へ転換するため、同社は現状の業務の仕組みや体制を抜本的に見直し、生産性の向上を目指すこととした。その主な取り組みは、工程管理、原価管理の方法の統一である。これは、複数の建設企業が経営統合したという経緯から、部門ごとに旧所属会社に根差した“組織文化”がある状況のもとで、それを克服し、全社員が目的意識の統一を図るためにも、不可欠な取り組みであった。
同社が進めようとしている、生産性向上を図るための取り組みは、現場に広く浸透させることが必要である。具体的な工程管理の方法について、経営者、管理者、現場監督、協力業者など、複数のメンバーが協議し、改善できる体制であることが望ましい。そこで同社は、高知市に本社を置き、建築物解体工事、土木工事、造園工事、産業廃棄物(キーワード解説)運搬などを手掛けている協力会社、(株)オアシス・イラボレーションと連携。コンサルティング支援のもと、生産性向上のベストプラクティス(キーワード解説)を確立するための、基盤づくりに着手した。
■社内や関係者間の目的意識を合わせれば、実現可能な生産性の向上
当連携体の取り組みは、今後、事業承継等の問題を抱えた建設企業が、他の建設企業と経営統合を行う際の、モデルケースになると思われる。合併・買収などを経た企業の経営改善をするにあたっては、異なる企業文化が混在しているため、通常よりも目的の共有に時間がかかる。だが、社内や関係者間で目的意識を合わせることができれば、通常の企業と同様に、生産性の向上を実現することが可能である。
■工程管理表、原価管理表の様式を統一、工程会議の定期実施もスタート
具体的な取り組みとして、まず工程管理表、原価管理表の様式を、(株)三谷組の社内で標準様式として統一した。また、これらの様式は、全ての現場について、同社の総務部が管理することとした。
さらに、今後はこの標準様式により工程管理、原価管理を行い、同時に作業工程が予定どおりに進捗しているかどうかを確認するため、定期的(週次、隔週、月次)に工程会議を実施することを決めた。新規に受注した案件については、着手時の工程会議で、工程及び実行予算の妥当性を検討する。これにより、経営者、管理者、現場監督、協力業者などが、同じ資料に基づいて打ち合わせや議論を行える体制を構築した。このように、複数の関係者が、定期的に工程管理に関与するようにしたことで、適時問題点の認識が共有され、その改善が早期に行なえる環境が整った。
完成した工事についても、「精算会議」を実施することとした。実行予算と実績とを比較することで具体的な問題点を明らかにし、全社的に共有できる体制を構築した。平成28年11月以降は、工程管理、原価管理上の問題点が、毎月フィードバックできる体制となっている。
■連解体内に、関係者全体で仕事を進める大切さへの理解が広まる
工程会議の実施により、一個人で仕事をするのではなく、つねに組織的な動きをするようになったことで、連携体内には関係者全体で仕事を進める大切さへの理解が広まった。
また、今回の取り組みの目標である、生産性向上とそれによる利益率の向上については、利益額を前年よりも増加させることができた。工程管理・原価管理の方法が全社的に統一され、これらが適切に実施できるようになったこと、及び現場監督以外の経営者・管理者が直接工程の改善に関与できるようになったことの、具体的な成果だといえる。
■統一された工程管理・現場管理の経験を、多くの現場で積み重ねることが今後の課題
今回の取り組みでは、協力企業も含めて、どのように全社的な目的意識の統一を図り、生産性の向上を図るかが課題であった。取り組みの開始当初は、管理者によって経営改善への目的意識に温度差があったが、情報共有のための会議を開催していくにつれ温度差が縮まり、全ての経営者・管理者が、一つの目標に向かって進める企業体制を構築することができた。
だが、工程管理及び原価管理の様式は統一されたものの、依然として現場監督によって力量の差が見られ、経営者・管理者の管理能力のレベルも、案件によってかなり相違が見られる。これらの状況を改善するため、多くの現場で、統一された工程管理、原価管理の経験を積み重ねていくことが、連携体にとって、今後の大きな課題である。
![]() 実行予算
実行予算
工事受注後にその工事をどのような予算計画で進めていくかを、工事の着手前に計数化したもの。工事のコストを管理し、利益を確保するために作成される。工事の詳細が決まった後、協力会社と発注金額の交渉を行うなどして作成されることから、工事原価総額の精緻な見積りといえる。
![]() 産業廃棄物
産業廃棄物
産業活動に伴って排出される廃棄物。その処理について、義務者や処分の方法などを規定する「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が
制定されており、産業廃棄物は事業者が自ら処理することが義務づけられている。
![]() ベストプラクティス
ベストプラクティス
ある結果を得るのに最も効率のよい技法、手法、プロセス、活動などのこと。最善慣行、最良慣行ともいう。なお、ベストプラクティスはある時点における最良の実践例であって、固定的な存在ではない。新技術の開発によってつねに変化し得る、流動的なものであることに留意する必要がある。
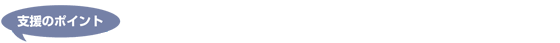
●現場を一個人に任せるのではなく、組織として仕事に取り組むことで、現場に生産性向上につながる知恵と工夫が生まれる体制づくり、環境の整備に取り組んだ。